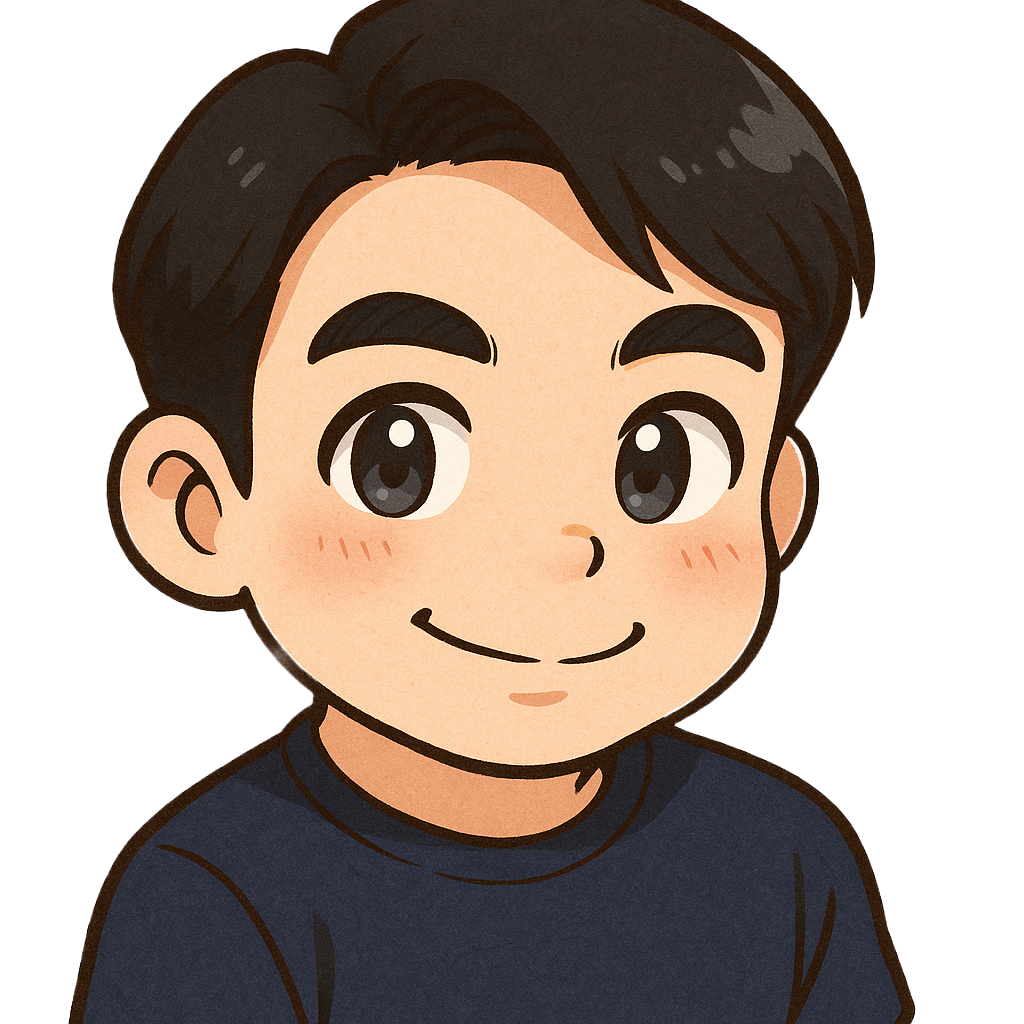
なおえもん
まいど、なおえもんやで
あれから31年という時が経ち、当時の記録や資料を改めて読み解いてみると、構造的な限界と物理的な壁が存在していたことが分かります。
あの日、消防・警察・医療・自治体の現場で一体何が起きていたのか。
なぜ初動は遅れ、機能不全に陥ったのか。
資料を基に、その要因を整理してみたいと思います。
もくじ
情報の真空地帯(発生直後~6時間)
消防:届かなかった119番
神戸市消防局の管制室。地震発生直後から、オペレーターたちの前にある電話ランプは一斉に点滅を始めた。しかし、ヘッドセットをつけた彼らの表情には戸惑いの色が浮かんでいた。
「もしもし、119番消防局です」「もしもし!」。
何度呼びかけても、受話器の向こうからは何も聞こえない。
これは「無応答電話」と呼ばれる現象だった。
この日1日だけで約2,700本に上ったこの無言の通報。
原因は消防局側ではなく、NTTの専用回線にあった。
通話音声を増幅して明瞭に伝えるための「伝送装置」が地震の衝撃で故障したのだ。
この装置が壊れると、故障を知らせる信号が自動的に消防局のベルを鳴らし続ける仕組みになっていた。
本来、火災発生をいち早く知らせるはずのシステムが、逆に消防局の回線をパンクさせ、市民からの助けを求める声を遮断してしまったのである。
結局、管制室が火災の発生を初めて知ったのは、長田消防署からの無線連絡によってであった。
「長田管内建物火災。川西通りと思われる」。
皮肉にもハイテク機器は沈黙し、現場からのアナログな報告だけが頼りだった。
神戸市消防局は、前年に設置したばかりの最新鋭の高所監視カメラに望みをかけたが、これも停電などの影響で作動しなかった。
消防局の片岡係長は、状況を目視で確認するため、エレベーターの止まった庁舎を飛び出し、隣接する市役所の24階展望ロビーまで階段で駆け上がった。
眼下に広がる街を見て、彼は言葉を失う。
「火柱が10箇所から11箇所。これは相当なダメージだ」。 ヘリコプターによる偵察も試みられたが、ヘリポートまでの道路が寸断されており、乗り組員が徒歩で向かったため、離陸できたのは発生から4時間近く経過した午前9時20分だった。
上空からの映像には、長田区を中心に20数箇所で黒煙を上げる街の姿が映し出されていた。
この情報が決め手となり、神戸市長はようやく県を通じて他府県への応援要請を行った。
火災発生からすでに4時間が経過していた。
警察:倒壊した拠点
治安維持と救助の要である警察もまた、甚大な被害を受けていた。神戸市兵庫区にある兵庫警察署。鉄筋コンクリートの庁舎は、1階部分が完全に押しつぶされ、見るも無残な姿となっていた。
潰れた1階には当直勤務の警察官10人と、留置場の被疑者10人がいた。
瓦礫の中から警察官9人は救出されたが、1人は遺体で収容された。
留置されていた人々も余震の危険があるため、別の署へ移送せざるを得なかった。
活動拠点を失った兵庫署員たちは、署の前の道路に机を並べ、青空の下で対策本部を設置した。
しかし、そこに寄せられるのは「家族が埋まっている」「遺体をどうすればいいか」といった悲痛な訴えばかり。
彼らは手探りでの対応を余儀なくされた。
一方、兵庫県警全体を指揮する県警本部は、埋立地であるポートアイランドの新庁舎に置かれていた。
しかし、ここで埋立地特有の「液状化現象」が発生する。
泥水が噴き出し、庁舎の床は水浸しになり、土台の一部が傾いた。
これでは対策本部として機能しない。
県警はポートアイランド庁舎の使用を断念し、古い生田警察署の庁舎に本部を移すことを決定する。
しかし、そこには災害対策用の電話回線などの準備が整っていなかった。
本部機能がようやく生田署で稼働し始めたのは、地震発生から4時間近くが過ぎてからだった。
自治体:参集できなかった職員
行政の要、神戸市役所。その高層ビルのひとつ(2号館)も中層階で折れ曲がるように崩壊していた。
8階に設置された災害対策本部は他の自治体への応援要請や被害状況の把握を行う総司令部である。
笹山市長が到着したのは午前6時半、午前7時に本部が設置された。
しかし、その場にいた職員はわずか10人余り。
神戸市の地域防災計画では「震度5以上の地震が発生した場合、全職員が参集する」ことになっていた。
だが、交通機関は完全に麻痺していた。
地震当日の夜までに出勤できた職員は全職員の約40%。
この圧倒的な人手不足が、初動体制の構築に致命的な遅れをもたらした。
特に被害の大きかった東灘区役所の状況はさらに深刻だった。
東灘区では1200人余りが亡くなったが、区役所に出勤できた職員はわずか20%にとどまった。
その理由は職員の居住分布にあった。
東灘区は古くからの住宅地であり、区役所職員の多くは、開発が進んだ垂水区や西区などの市西部に住んでいたのである。
区内に住み、すぐに駆けつけられる職員は全体の12%に過ぎなかった。
午前8時、市税課の内藤さんが区役所に到着した時、そこにいたのはわずか4人だった。
「マニュアルも何もない。とにかくやれることをやろうと」。
彼らは手分けをして、指定避難所となっている40箇所の建物が無事かどうかの確認に走り出した。
しかし、避難所となるはずの公民館などは倒壊したり、すでに鍵が壊されて住民が避難していたりと、想定はことごとく崩れていた。
医療:崩壊した救命の砦
医療機関の被害も深刻だった。神戸市内にある1419の病院や診療所のほとんどが、通常の診療機能を失っていた。
地域の中核病院である12の病院が倒壊、あるいは全焼した。
灘区にある金沢病院(188床)。
地震直前、当直医たちは心臓発作を起こした患者の緊急手術を行っていた。
しかし激しい揺れと共に停電。人工呼吸器が停止し、その患者は亡くなった。
自家発電装置に切り替えたが、それも30分で原因不明の停止。
レントゲンも手術室も使えなくなった。
薬品庫は棚が倒れて扉が開かず、手元にあるのはわずかな消毒薬と抗生物質、そして針と糸だけだった。
午前10時。倒壊した家屋の下から救出された怪我人が、戸板や畳に乗せられて次々と金沢病院に運び込まれてきた。
近くの寮から駆けつけた看護婦たちは、私服のまま路上で心臓マッサージを繰り返した。
午前中だけで300人が運び込まれたが、その半数近くがすでに息を引き取っていた。
ロビーは怪我人で溢れ返り、午後には縫合用の針さえ底をついた。
医師や看護婦たちは、近くの河原で焚き火をおこし、一度使った針を煮沸消毒して再利用した。
骨折した患部の固定には、ギプスがないため、ダンボールや雑誌を代用した。
「運ばれてくる方を見るだけで疲弊していく中で、病棟の患者さんも徐々に悪化していく。自分は何もできないという無力感、絶望感しかなかった」(金沢病院・長野医師)
拡大する被害と阻まれた応援(発生6時間~12時間)
消防:水がない、届かない
午後になり、火災の勢いはさらに増した。特に木造住宅が密集する長田区では、火災旋風が巻き起こり、火は西へ西へと燃え広がっていた。
長田消防署にようやく他都市からの応援部隊が到着し始めたのは、午後1時半。
大阪市消防局の10台だった。
しかし、彼らを待ち受けていたのは「水がない」という現実だった。
地震による断水で消火栓は使えず、防火水槽の水もわずか30分で枯渇していた。
「40トンや100トンの水ではどうしようもない。もう海の水しかない」(長田消防署・魚住副署長)。
海から火災現場までは約2キロメートル。
消防車1台が水を送れる距離は約300メートル。
つまり、海から現場まで水を送るには、少なくとも5台以上の消防車を連結し、中継送水する必要があった。
「海へ向かえ!」。
魚住副署長の指示で、応援部隊は海を目指した。
しかし、ここで「交通渋滞」という巨大な壁が立ちはだかる。
避難する車、安否確認に向かう車で道路は埋め尽くされていた。
消防車は現場にたどり着くことさえ困難で、隊員たちは交通整理をしながらホースを延ばさなければならなかった。
ホースの連結作業が始まったのは午後9時過ぎ。
完了までに3時間近くを要した。
しかも、渋滞する車が道路上のホースを踏みつけ、次々と穴が開いていく。
震災後に長田消防署に残されたホースの山は、その3分の1が破損していた。
穴が開いたホースでは水圧が上がらず、先端のノズルからはチョロチョロとしか水が出ない。
猛火を前に、消防士たちは危険を冒して火元に近づかざるを得なかった。
無線もまた機能不全に陥っていた。
全国から100以上の消防本部が応援に駆けつけたが、異なる組織間で連絡を取り合うための「全国共通波」は1波しかなかった。
100隊以上が一斉に同じ周波数を使おうとしたため、無線は混信し、全く使い物にならなくなった。
海側のポンプ車と現場の放水隊との間で「水圧を上げろ」「下げろ」といった連携が取れない。
隊員たちは2キロの道のりを何度も走って往復し、伝令として情報を伝えるしかなかった。
「ハイテクの時代に、足で稼ぐしかなかった」(和歌山市消防局・坂東一次長)。
警察:機能しなかった交通規制
渋滞は、消防だけでなく全ての救援活動を阻害していた。兵庫県警は「災害対策基本法」の適用を急いだ。
これは緊急輸送ルートを指定し、一般車両を強制的に排除する強力な措置である。
しかし、その実施には「標識の設置」という物理的な壁があった。
施行令により、規制を知らせる標識のサイズや形状が事細かに定められていたのだ。
県内にその在庫はなく、新たに300枚以上を作成する必要があった。
県警が山形県の標識メーカーに発注できたのは18日の夕方。
「1日でなんとかしてくれ」という無茶な注文に工場はフル稼働したが、印刷が完了したのは20日の朝。
実際に標識が設置され、法的な規制が効力を発揮したのは、地震発生から4日後のことだった。
その間、警察官は倒壊の危険がある国道2号線のガード下などを避け、手探りで「通れる道」を探し、拡声器で一般車両に協力を呼びかけることしかできなかった。
自治体:情報の錯綜とパニック
18日未明、新たな危機が発生した。東灘区の埋立地にあるLPG(液化石油ガス)タンクからガス漏れが確認されたのだ。爆発すれば市街地まで被害が及ぶ。 午前6時41分、東灘区役所はタンクから半径2キロ、約7万人の住民に対して「避難勧告」を出した。 「二次災害でこれ以上被害を出してはならないという懸念があった」(東灘区・金治区長)。 しかし、避難勧告区域のすぐ外側にある避難所には、行き場を失った住民が殺到し、パニック状態となった。屋外の公園に座り込む人々。寒さと飢え、そして情報不足。「いつまで待てばいいのか」「何が起きているのか」。住民の苛立ちは頂点に達していた。 現場では、漏れたガスをポンプで隣のタンクに移す応急処置が行われていたが、その情報は住民には伝わらなかった。区役所もまた、詳細な現場情報を把握できていなかったのである。 結局、混乱を恐れた区役所は、勧告からわずか10分後の午後6時半に「一旦解除」という苦渋の措置を取らざるを得なかった。
命の選別と転送の壁(発生12時間~48時間)
クラッシュ・症候群(挫滅症候群)の恐怖
金沢病院をはじめとする被災地の病院では、新たな死の影が忍び寄っていた。「クラッシュ・症候群(挫滅症候群)」である。
倒壊した建物や家具の下敷きになり、長時間圧迫された筋肉が壊死する。
救出されて圧迫が解かれると、壊死した筋肉からカリウムやミオグロビンといった毒素が血液中に一気に流れ出し、腎不全や心停止を引き起こす。
一見すると外傷が少なく、救出直後は元気そうに見える患者でも、数時間から数日後に急変して死に至る恐ろしい症状だ。
特徴は、尿が褐色に変わること。
金沢病院に運び込まれた患者の中にも、この症状を示す人々が増えていた。
彼らを救うには、人工透析などの高度な治療が必要だが、病院の機能は失われている。
助かるはずの命を救うには、被災地外の病院へ「転送」するしかなかった。
断ち切られたライフライン
しかし、ここでも「情報」と「交通」の壁が立ちはだかった。通常、こうした広域搬送は消防の救急車が行うが、被災地の救急車は出払っており、通信網の寸断でどこの病院が受け入れ可能かも分からない。
厚生省(当時)は17日の段階で、ヘリコプター搬送を受け入れる病院のリストを作成し、被災地へFAXを送っていた。
しかし、電話回線の寸断により、肝心の金沢病院にはその情報は届いていなかった。
大分県別府市から駆けつけた佐藤さんは、金沢病院で治療を受けている大学生の長男の足が異常に腫れ上がり、尿の色が変わっていることに気づく。
「このままでは息子が死んでしまう」。
彼女は別府の知人医師を通じて、大阪の病院への転送を模索した。
連絡を受けた大阪市立総合医療センターの月岡医師や林下医師たちは、異例の決断をする。
「怪我人が来るはずなのに来ない。もっと何か起きているはずだ」。
彼らは受け入れ体制を整え、自ら救急車に乗り込んで神戸へ向かうことさえ試みたが、渋滞に阻まれ、往復に3時間以上を費やした。
制度の壁と個人の突破
「大阪市消防局の救急車を神戸へ出してほしい」。総合医療センターは要請したが、大阪市消防局の回答は「法的に、現地の消防本部からの要請がない限り出動できない」というものだった。
ここでも行政の縦割り構造と硬直したルールが壁となった。
しかし、現場の医師たちは諦めなかった。
芦屋市で開業医をしている上塚医師は、自身の診療所が半壊する中、大阪市消防局の救急車が通りかかるのを偶然見つけ、直接交渉して患者のピストン輸送を開始した。
また、金沢病院の長野医師は、公衆電話から必死に連絡を取り続けた。
そして、佐藤さんの母親のルートを通じて、ついに大阪市立総合医療センターとの連絡がついた。
19日午前0時。
月岡医師は、被災地に出動していた陸上自衛隊のヘリコプターに患者の転送を依頼する。
しかし、ヘリの準備ができても、それを金沢病院に伝える手段(電話)が通じない。
そこで月岡医師は、奇策に出た。
大阪市消防局から専用回線で神戸市消防局へ、そこから灘消防署へ連絡を入れ、最後は灘消防署員が「走って」金沢病院へ伝令に向かったのだ。
「ヘリが来る!」。
この情報がもたらされたのは、夜明け前だった。
19日午前7時。金沢病院近くのグラウンドに自衛隊のヘリコプターが着陸した。
地震発生から50時間が経過していた。
クラッシュ・症候群の患者5人を含む8人が、ヘリで大阪へと搬送された。
彼らは一命を取り留めた。
災害時の救急医療において、最初の3日間(72時間)が勝負と言われる中、ギリギリのタイミングでの搬送だった。
72時間の教訓
1月17日の夜が明け、18日、19日と時間が経過するにつれ、神戸の街は少しずつその傷跡の深さを露呈していった。長田区の火災は18日未明にようやく鎮火したが、約50ヘクタール、4700棟以上が焼失した。
最終的な死者数は6434人(関連死含む)。
その多くは、建物の倒壊による圧死や窒息死だったが、助け出された後に亡くなった人、治療が間に合わずに亡くなった人も少なくない。
この72時間の記録が浮き彫りにしたのは、想定を超えた巨大災害の前では、既存の防災システムやハイテク機器がいかに脆く崩れ去るかという現実だった。
- 通信の途絶: 119番のパンク、専用回線のダウン、無線の混信。情報が伝わらないことが、初動の遅れと混乱の最大の原因となった。
- 交通の麻痺: 道路が塞がれれば、消防車も救急車も物資も届かない。法的な規制も標識がないために後手に回った。
- 組織の硬直性: 「要請がなければ動けない」「管轄外」という平時のルールが、緊急時の柔軟な対応を阻んだ。
孤立無援の中で近隣住民を指揮して救助にあたった消防士。
麻酔なしで治療を続けた負傷した医師。
法的根拠を超えて救急車を動かそうとした医療スタッフ。
そして、知人のネットワークを駆使して命を繋いだ家族たち。
システムが崩壊した時、最後に人を救ったのは、人の「何とかしたい」という強い意志と行動力でした。
この72時間の教訓は、その後の日本の災害対策、救急医療体制、そして私たちの防災意識を根本から変える出発点となったのです。
しかし、これは決して「終わった歴史」の話ではありません。
「古い住宅はあまりない」と思われがちですが、実際には1981年以前の「旧耐震基準」で建てられた木造住宅は、日本全国にまだ数百万戸単位で残っています。
2024年の能登半島地震でも、多くの古い木造家屋が倒壊し、建物の下敷きになって亡くなった方や、長時間挟まれた方が多数いました。
地方都市や都市部の密集地では、依然として倒壊リスクの高いエリアが存在します。
さらに、家屋倒壊とそれが引き起こす「火災」の恐怖も忘れてはなりません。
阪神・淡路大震災では、倒壊した家屋が道路を塞いで消防車の到着を阻み、木造密集地を焼き尽くす火災旋風が多くの命を奪いました。
能登半島地震においても、輪島朝市周辺の大規模火災が同様の悲劇を招いています。
この現実は、近い将来必ず起こるとされる「首都直下地震」においても、我々に重い課題を突きつけています。
首都圏には、戦後の高度成長期に建てられた古い木造住宅が密集する地域(木密地域)が広範囲に残されています。
もしそこで激震が発生すれば、阪神と同じように数多くの建物が倒壊し、同時多発的な火災が発生することは避けられません。
瓦礫の下で動けないまま迫りくる炎に巻き込まれる恐怖、そして、なんとか炎を逃れても、長時間圧迫された身体が「クラッシュ症候群(挫滅症候群)」を発症し、搬送もままならずに命を落とす――。
道路が塞がり、水が止まり、病院が機能不全に陥る中で、いかにしてこの複合的な危機から命を守るのか。
阪神の72時間で起きた「助かるはずの命が失われる」という悲劇は、決して過去のものではなく、今の私たちの足元にある、差し迫った未来の姿かもしれないのです。


